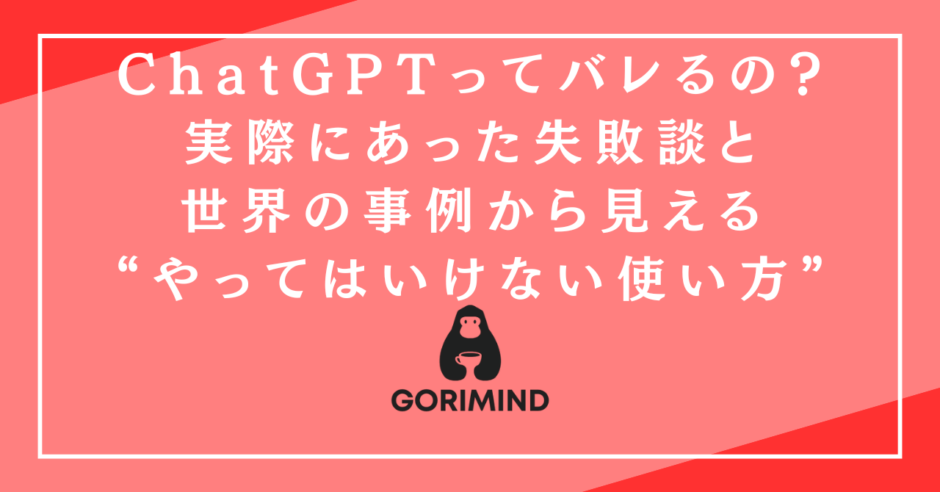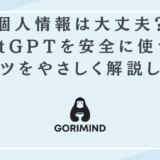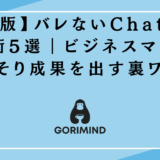こんにちは、ゴリパパです。
最近、よくこんな声を聞きます。
「ChatGPTって、バレたらヤバくない?」
「レポートとかメールに使ってるけど、これって問題あるのかな…?」
「そもそも、会社や大学で使ってもいいの?」
正直、こういう不安はめちゃくちゃよく分かります。
実際、僕の身の回りでも、ChatGPTをめぐって“怒られた”“問題になった”という事例が、何件も起きています。
エンジニアがコピペしてバグ量産。怒鳴られた
ある若手エンジニアが、ChatGPTに「このAPIどう繋ぐ?」と質問し、出てきたコードをそのまま貼り付けました。
見た目は正しそう。でも動かない。バグだらけ。
「それ、ChatGPTからコピペした?」と聞かれ、正直に「はい」と答えたところ、上司からこう一言。
「お前はAIの外注先か?」
笑えないけど、ありがちな話。なぜか?
ChatGPTは“あなたのプロジェクトの背景”なんて知らないからです。
法務部員、契約書を丸コピで提出→クライアントから大激怒
別の知人は、ChatGPTで契約書のたたき台を作らせ、
そのままクライアントに提出してしまいました。
ところがそれがテンプレすぎて、細かいニュアンスが全然違った。
結果、「これはどこかからコピーしたものですよね?」と詰められ、信頼を失いました。
AIが作った文章は、一見それっぽく見えても、法律の“現場”には通じない。
これは肝に銘じるべきです。
顧客リストをAIに入力して社内で問題化した営業社員
さらに衝撃だったのは、営業の若手がChatGPTに「顧客提案文」を頼む際、
社名・担当者名・取引内容を丸ごと入れてしまったケース。
履歴を見た上司が真っ青になり、社内でAI利用ポリシーが即日制定される流れに。
AIはクラウド上で動いており、一度入力した情報が外部に渡るリスクがある。
本人は悪気がなかったけど、これはもう「使い方のリテラシー」の問題です。
🔎 海外でも“やらかし”は増加中──数字が示す現実
僕の身近だけでもこんな事例がある中で、海外でも同様の失敗が相次いでいます。
📘 学術分野での事例
- 2023-24年、イギリスの大学で約7,000件のAIチートが確認されました。
出典:The Guardian(2024年報道) - 88%の学生がAIを何らかの形で課題に利用しているという調査結果もあり、
大学側が検出しきれていない現実があります。 - アメリカ・ノーザンミシガン大学では、教授がChatGPTで書いたエッセイを見破り、
学生に再提出を命じた事例も発生。 - さらに、リーディング大学の研究では、AIが生成した課題の94%が検出されなかったという衝撃のデータも。
これはAI検出ツールの限界を示しています。
🧠 つまり、「バレないこと」もあるけど、「一発でバレること」もある。
**絶対にバレないわけでも、絶対にバレるわけでもない。**だからこそ使い方が重要なんです。
🧑💼 職場でも“AIの使い方”で職を失う人たちが増えている
- 英国のコピーライター、**アナベル・ビールズさん(49歳)**は、ChatGPTが導入された結果、仕事を失いました。
会社がAIでブログ記事を自動生成し始め、彼女の担当業務が不要に。現在は別業界で働いています。 - ノラン・クラークさんは、業務中のメール作成にChatGPTを使った結果、会社のポリシーに違反し解雇。
「顧客とのパーソナルなやり取りにAIを使うことは許されない」と判断されたのです。 - AppleやSamsungのような企業は、社内の情報漏洩を懸念してChatGPTの使用を全面禁止にしています。
🤖 「使うのが怖い」と思うのは当然。でも…
ここまで読むと、「やっぱり使うの怖いわ…」って感じるかもしれません。
でも、それは正しい反応です。怖がることは、むしろ“正常”。
怖がった上で、「どう使うか」を考えればいいんです。
ChatGPTは便利なツールです。
僕は毎日使っています。文章作成、構成チェック、商品説明の草案、エラー調査、アイデア出し。
人に聞くより速いし、気まずさもないし、なにより、アウトプットを“加速”してくれる。
これは一度味わったら手放せません。
✅ まとめ:ChatGPTは“バレるか”じゃなく、“どう使うか”
バレる・バレないを基準に使うのではなく、
「自分が責任を持てる使い方か?」を基準にすれば、迷いは減ります。
- 顧客情報は絶対に入力しない
- コピペではなく、自分の言葉でリライトする
- 書いた内容に責任を持つ
- 規約がある場合はしっかり読む
これが“怖がらずに使う”ための最低限のマナーです。
✏️ 最後に:あなたは、“使われる人”になる? “使う人”になる?
ChatGPTは、「うまく使える人」と「使われる人」を分ける時代の分岐点にいます。
その境界線は、「リスクを理解したうえで使えるかどうか」。
つまり、ただ便利だから使うのではなく、“考えて使う”ことが求められているんです。
あなたには、その力があるはずです。
AIに振り回されるのではなく、AIを味方にできる人間になりましょう。
 ゴリパパ式キャリアアップ術
ゴリパパ式キャリアアップ術